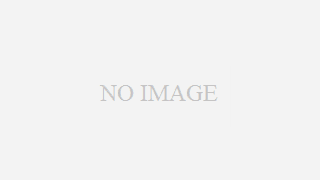大石理紀、29歳。北海道で生まれ育ち、今は、派遣社員でとして総合病院の事務の仕事をしている。東京での暮らしは、苦しい。古いアパートの家賃を払ったら、手元には6万ほどしか残らない。古着を買い、安売りの食材をやりくりして、なんとか暮らしている。
リキの友達のテルも、同じような非正規労働者だ。大学の奨学金返済のため、風俗でアルバイトをしている。貧困が彼女たちを蝕む。
そんな時、卵子提供、代理母の話が舞い込む。
取り柄もなく、何の資格もない女たちが生きていくためには、自分の卵子や子宮を売るしかないらしい。
リキは、有名な元バレエリーナ草桶基の子を産むことになる。
精子を体内に入れて妊娠させる人工授精の方法をとることになった。ビジネスだと割り切ろうとする一方、自分の体と心は常に違和感でいっぱいになる。
子を産む機械のように扱われること。人としての自分。妊娠してわかる動物としての自分。
その間、リキは多くの矛盾や疑問に悩まされることになるのだが、悠子の友人、春画作家のりり子の仕事を手伝うことで、自分を見つめていくのである。
男と女の差。妊娠するということ。子どもの存在。様々なこと考えさせてくれる小説だったが、全編、主人公はカタカナでリキと表記される。
北海道で生まれたとか非正規労働者であるとか、理紀を構成する様々な要因を取り外して、一つの人間として事柄に対応していく様が、この表記によく現れている。
もう一つ、リキが女性用の風俗をするダイキとプレイをするシーンがあり、そこでリキが思うことが、この小説の肝であるように思う。
リキは、ダイキを金で買うのである。風俗に勤める女性は自分の気持ちを安定させるため、ホストクラブに通ったり男を買ったりすると言われているが、リキも自分の心の安定を求めると、やはり、男とセックスがしたいと思うのである。
その時に友だちの紹介で、ダイキを買うことになるのだが、初めて会ってホテルにいく時に、命に危険はないのかと思う。女は買われる時も反対に買う時も、生命の危機を感じる。
男と女の性差と言ってしまえばそれまである。しかし、春画画家のりり子の仕事を手伝っている時、リキは言う。
「お楽しみの後で女だけが苦労を背負うのはおかしくないですか」
男と女がセックスを楽しんだとしても、その後の肉体的負担を受け持つのは女である。妊娠出産が女の体を痛めつけ、命に関わる大仕事になるのに。
そういえば、ここに出てくる男たち、基もダイキもリキの昔の恋人たち誰も彼も、自分勝手で女を踏みにじる言動が多い。
その上でリキが妊娠や出産について語ることは、一つの救いとなるように思うが、これは読んだ人がそれぞれ考えることかもしれない。
とにかく、重い小説である、だけれど、救いのある小説のように私には思えた。