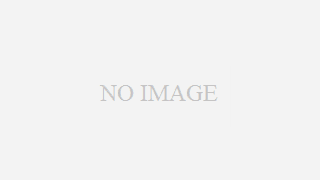小学校で子どもたちが学習をするのを見ていると、計算の力が大切だなあと思います。
私の知っているいくつかの小学校の実態として、計算の力が育っていないように感じます。
計算、と言っても、「3+5」とか「7−4」とか、そんな簡単なものです。
対象となるのは、小学校1年生。
ではなく、2年生、3年生といった学年です。
計算が全くできないわけではなく、「流暢に」ということです。
指を折り曲げたり数えたりして、答えを出している子どもの、なんと多いことか。
なんなら、鉛筆を机の上にたくさん並べて、それを数えている子どももいます。
教師は、答えが合っていれば、それでできていると判断してしまいがちです。その過程にも目を向けなくてはいけないのですが、なかなか、余裕がありません。授業中、教室を飛び出して行ってしまう子どもがいたり、体調不良を訴えてくる子もいたりして、その対応に追われます。
5+6といったくり上がりのある計算、15−8といった繰りさがりのある計算も、スムーズにはできていない子が多いようです。「3+5」とか「7−4」がスムーズでないのに、当然と言えば当然ですが。
ただ、世界に目を向けると、アメリカなどに比べると日本の子どもの計算力は高いそうですので、日本中の子どもの計算の実態ではありません。
岐阜県の小学校は、計算ドリルの同じ問題を3回はする、と聞いたことがあります。
ここで暮らしているお母さんに話を聞きますと、「子どもは3回すると思ってドリルをしているから、計算するのがとてもスムーズだ」と言っておられました。
計算が苦手な子供もいるでしょうが、回数を積み上げれば、ある程度、そのことは解決できるのではないかと思われます。
最近は「その子の特性を理解すべきだ」「配慮をすべきだ」という声をよく聞きます。
計算が苦手な子に、計算練習をさせるなんてもってのほか、ではあります。
本当は個々の子どもの得意不得意をつかんで、量を調整していくのが大事で、一概に、計算練習はしなくていいです、と言うのとは違うのですが、「嫌がる子に無理やりさせるなんて」となるのが困るため、教師側は控えてしまうところがあります。
ただ、学校生活はもう少し続きますよね。中学校、高校、なんなら、将来を視野に入れて専門学校や大学も進路としてはあるかもしれません。その場面で、計算が非常に全く苦手で、進路が狭まってしまうのは、とても惜しいことです。
また当の子どもたちは、わかりたい、できるようになりたいと思っているのです。学年が進んで、割合だの円の面積だのの算数問題、中学校の因数分解などは、基本的な計算の力は必要ですが、そのころに基本的な計算練習を積んでも、なかなか、成果は上がりにくいのではないかと思います。
それに何より、ある程度、計算ができるようにしておかないと、社会生活で困ることが起こりやすいです。
計算機やICTを活用するにしても、大まかな計算が大体できることはとても大事です。
では、計算の力はどうしたら積み上がるのか。
やっぱりやるしかない、という所はあるでしょう。
私は、いかに学力をつけるかを考えるあまり、色々な学習塾のやり方などを少し調べたことがあります。
向こうも商売なので、親切には教えてくれませんが、自分の子どもが体験入塾した時の様子を見たり、塾に行っている子に話を聞いたりしていると、大体わかってきます。
一言で言えば、昼寝をして賢くなっている塾はない、と言うことがわかりました。
色々なやり方がありますが、とにかく、積み上げをしていくというのがほとんどでした。
計算はめんどくさいので、子どもたちは嫌がります。
教師側としても、その採点をし、間違ったところをやり直させるのは大変です。
宿題が多いと保護者からクレームも来ます。
親も面倒、子も面倒、教師も面倒。
三方面倒なら、計算練習を減らすのが一番です。
こうして、計算が苦手な子どもたちが増えていくのではないか、とこの頃思っています。